開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
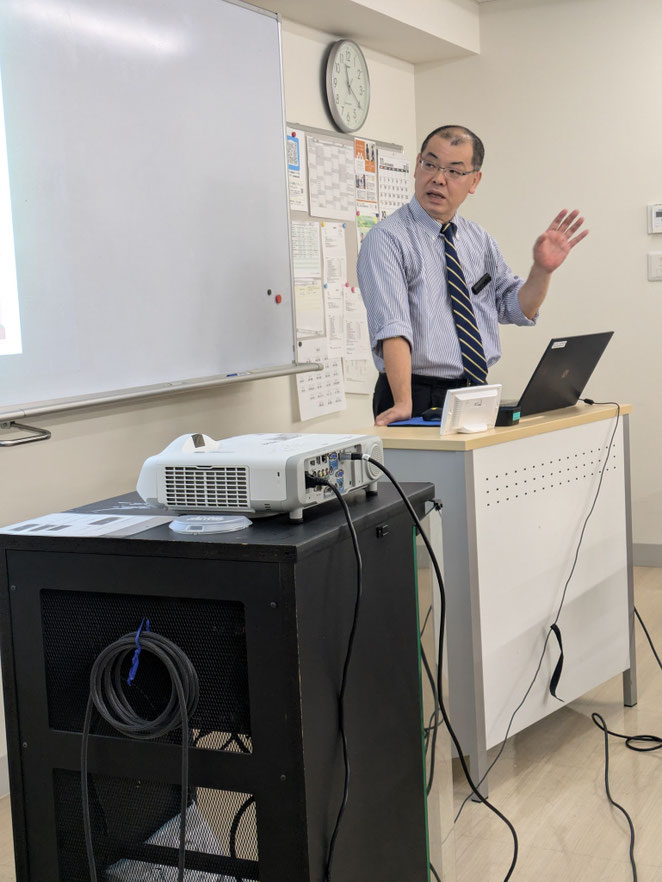
昨日9月5日に母校である東京呉竹医療専門学校鍼灸マッサージ教員養成科で2年生を対象とした特別授業を内原先生とともに担当しました。年に一度行われる授業で、今回で9回目となりました。内原先生と私で1コマを半分ずつ講義します。先に行う内原先生の話を私は教員養成科学生さんとともに聞きます。今年も内原先生のパートについて触れていきましょう。
関東鍼灸専門学校の副校長を務めた内原拓宗先生。関東鍼灸専門学校で鍼灸師国家資格を取り、東京呉竹医療専門学校(※当時は東京医療専門学校)鍼灸マッサージ教員養成科25期として入学します。ちなみにですが、私が鍼灸マッサージ師になり、そのまま教員養成科に進学したら同期になっていました。内原先生の25期には私の本科(鍼灸マッサージ科)同期が2名います。私が教員養成科に進学したのは30期。鍼灸マッサージ資格を取ってから5年空いており、その間に柔道整復師を取り臨床経験を積んでいました。つまり東京呉竹医療専門学校教員養成科は私達にとっての母校であり、先輩後輩の間柄になります。
関東鍼灸専門学校を退職した内原先生は千葉大学医学部に席を置きながら、千葉大学医学部付属病院和漢診療科鍼灸外来、諏訪の杜整形外科・附属鍼灸院、なのはなクリニック鍼灸外来と医療機関に関連する場で臨床をしつつ市井のハリトヒト。鍼灸院にも勤め、非常勤講師として古巣の関東鍼灸専門学校でも教壇に立っています。
昨年の内原先生が出した講義テーマは「医療施設での鍼灸の可能性」。元々2017年に行った最初の特別授業は「鍼灸師のSNS活用」というテーマで、専門学校専任教員(内原先生)と開業鍼灸師(甲野)の立場でそれぞれ話すというものでした。そこから内原先生は医療機関(千葉大学医学部附属病院)で鍼灸施術をするようになり医療施設との関りがテーマになっていきました。そして今年のテーマは「医療の中での鍼灸」でした。昨年に比べて、医療施設から医療に、可能性というワードは消えて。施設を超えて医療全体における鍼灸について。可能性という文字(概念)が消えたのには、内原先生が本授業で伝えたかった<鍼灸はまだまだ可能性がある>ということと関係するのでしょう。“可能性がある”と断言する以上、テーマに可能性を入れる必要はないということだと思います。
複数の医療機関(=病院、クリニック)で勤務する内原先生。その生の声、実情が聞けました。私もあじさい鍼灸マッサージ治療院を開業してからの3年間は週に一度地方の大学病院で鍼灸師として勤務していた経験があります。内原先生の話を聞くと、約10年前と今では状況が変わっているところもありますし、全く変わっていないところもあると感じました。特に大学病院は研究、教育が臨床の上にくる場所。そのことは経験しないと実感がわかないことです。市井の鍼灸院で働く、開業するという経験だけだと理解に苦しむことがあるでしょう。シビアな現実、リアルな本音が出ていました。
「医療の中での鍼灸」において現状と課題を挙げています。まず医師側のものとして「医師の鍼灸の理解度」。医師側は鍼灸をどれくらい理解しているのか。理解向上のために医学部生への鍼灸実習が必要だと言います。千葉大学医学部では5回生のときに漢方を含めた実習を行っています。そして医師は鍼灸治療が適応と考えたとしてもどこに紹介したらよいのか分からないということ。これも理解度に直結することですが鍼灸師の質が判明しない。これは安全を担保する上で必須なのですが、医師のように実績が可視化されないことが鍼灸師には多いです。そして医療機関で医療従事者と共に働く医師にとって、果たして鍼灸師は医療従事者の一員なのかという不安もあるでしょう。私も大学病院にいたので身をもってこれらの課題を実感しました。
続いて鍼灸師側の課題。医療の外で活動してきた経緯から脱却できない。鍼灸も医療だろうという声はもっともですが、医療機関で医師の指示の下業務を行うのではなく、開業権があり多くの鍼灸師が医師とは独立して業務を行う鍼灸師は“医療の外”という状況です。医療機関と施術所の違いは大きいのです。設備が医療法で規定される要件を満たす医療機関とあはき法で規定される施術所。歴史的に視覚障害者の生業として鍼や按摩があったことから、特例といってかまわないほど設備要件はぬるいと私は感じています。衛生管理面や電子カルテ未導入といった点にそれが現れます。医師や医療機関の水準(常識)から比べると多くの鍼灸師が普段行っている活動は解離しているといえるのです。カルテ記入は他の医療従事者が読んでも理解できること。我々が常識として扱う東洋医学の知識や概念はときに暗号のようなものに映るのです。今年も内原先生が挙げていた、東京大学大学院にいて、現在は新潟医療福祉大学にいる粕谷先生の言葉、入り口と出口はしっかり現代医学と接続させる、という。
また今回の授業で興味深かったのが内原先生の医学部生に対するアンケート研究。鍼灸実習の授業前後で10項目のアンケートを医学部生に取り、データを集計・解析したもの。学会で発表したものを紹介しました。詳細は書きませんが、一つ興味深かったことを簡単に触れます。アンケートは5段階から選択するのですが、<どちらともいえない>の項目が授業前後で数値が大きく変わったといいます。<どちらともいえない>はよく分からないので判断がつかないということ。興味がないので判断する気もおきず玉虫色の答えにしておこうという思考が選択させる項目とも考えらます。この数値が変わったというのは良し悪しがありますが、鍼灸が医学部生にとって理解が進んだといえるだろうということ。いわば授業前は「鍼灸はよく分からないな」から授業後は「鍼灸は素晴らしい!」あるいは「鍼灸なんて怪しい」へ。どちらにせよ関心が持たれた結果。データの考察方法も含めて興味深いですし貴重な結果です。私もそうですが1年間をかけて経験を積んだものを特別授業に出します。毎年内容に変化があるのが聞いていて面白いです。
医療機関で働き、医療の中での鍼灸を模索している内原先生。教員養成科2年生はこれから卒業研究が本格化する時期。卒業後に教員になる者、開業する者、医療機関で勤務する者、様々な進路があることでしょう。専任教員を経て医療機関での職務をしている内原先生の言葉は重みがあります。そしてフリーになり行動しやすくなっている。授業後に複数の生徒が相談や挨拶に来ている姿をみました。
甲野 功

 大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
コメントをお書きください