開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
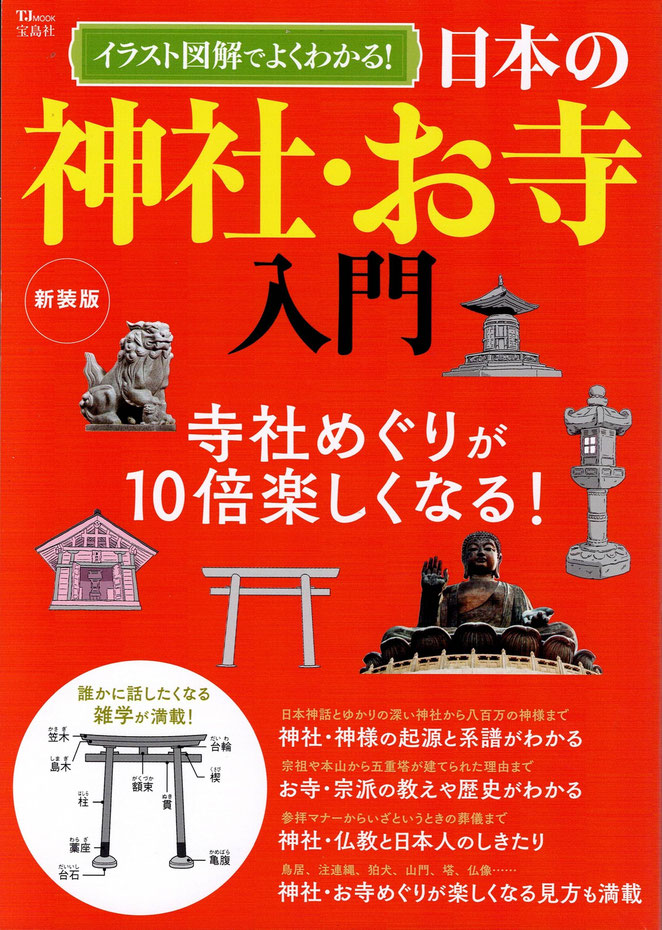
神社仏閣をよく巡ります。よく考えるのが神社かお寺か。神社だと思っていたらお寺でした。その逆も。このような勘違いがたまにあります。かなり知っているつもりですが、神社と寺院の区別がとてもつきづらいです。芸人で神主でもある狩野英孝氏は数えきれないほど神社とお寺の違いを問われ、そして間違った認識をされてきたと番組で語ります。彼は東北の神社、神主の家系に生まれましたが、散々それはお寺だよ!ということを言われてきたそうです。それは仕方ないことかとも思います。日本人でも神社と寺院の区別をはっきり説明できる、認識している人は多くないでしょう。私もそのところが分かるようになったのは30代を越したくらいでしょうか。そもそも神道(神社)と仏教(寺院)で宗教が異なります。そうなのに一緒に見えてしまうのか。その答えは神仏習合にあるわけです。
神仏習合とは神道の神様と仏教の仏様を同一視して融合される考えと行動。日本固有の神道に、大陸から渡ってきた仏教が融合していきます。これは世界的に見ても稀有なことではないでしょうか。神仏習合は明治維新のときに新政府の神仏分離令により分けられることになります。それに伴い廃仏毀釈という仏像を破壊する動きが各地で勃発。何百年と続いた思想が崩れます。それでも日本に根付いた神仏習合は庶民に根付いたままで今日に至っているから神社と寺院の区別がつかないのでしょう。神道と仏教がどのように混ざり合っているのか。それを考えてみたいと思います。
イラスト図解でよくわかる! 日本の神社・お寺入門
宝島社
この本に事例が載っていてとても勉強になりました。神仏習合の具体例を紹介していきます。
改めて、神道と仏教は異なる宗教。神道は日本固有のもので、仏教は古代インドで誕生し日本に入ってきた宗教になります。仏教伝来は538年あるいは552年ともされています。そのうちに日本の神は仏法の守護神とする考えが生じ、日本の神を鎮守(霊的な災いから土地や施設を守る神)として勧請し寺院内に祭るようになるのです。神が仏法の守護神という発想が非常に日本的だと感じてしまいます。海外からの文化を柔軟により入れて独自のものしてしまう我が国らしいという。
まず神仏習合によって変化したのは神社の明かり。石灯篭や提灯によって夜の神社に明かりがともります。実はこれが仏教の影響なのだとか。もともと神道は闇を大切にしており、重要な儀礼を深夜に行ってきました。伊勢神宮で20年に一度行う式年遷宮では、御神体を新しい社に移すのは真夜中です。対して仏教では闇は人間が迷う存在と捉えるため、闇を照らし出す仏の知恵が提灯の明かりと考えます。神社に灯籠が置かれるようになったのは仏教の影響を受けてのこと。
仏教と神道の大きな違いとして偶像崇拝の有無があります。神社の神棚には鏡が備えられていることが多いです。御神体が石、山、木など自然物であることも珍しくありません。神様は本来姿が見えないもので万物に宿るというのが神道の考え方。仏教では仏像があり本堂に安置されていることが多いです。元来は仏教でも仏像を作ることが禁止されていましたが時代が進むと仏の教えを広めるために仏像が作られるようになります。その仏教の影響により神道でも神像が作られるようになります。まさに神仏習合の表れでしょう。奈良県の東大寺には「僧形八幡神坐像」が所蔵されています。八幡神という神様が僧侶の形をしています。個人的な感想として、混ざるにもほどがあるという気がしてします。これには本地重遊説が関係しています。本地重遊説では、日本の神は仮の姿で現れたものであり本来は仏である、とします。仮(権)に神の姿で現れた“権現”と呼ばれます。
その八幡神ですが、全国で最も数の多い神社は八幡信仰の神社であり、その総本宮は大分県の宇佐神宮。奈良時代に東大寺の大仏建立にあたり、宇佐神宮は建立費を送っています。朝廷はこの援助に対して八幡神へ「八幡大菩薩」の神号を与えています。八幡神は朝廷とつながって大分から中央に進出すると武神として広く信仰され、日本中に勧請されていくのです。鎌倉のランドマークである鶴岡八幡宮は江戸時代まで仁王門や大塔、鐘楼、薬師堂などが立ち並び、神社というより寺院のような光景だったといいます。
権現は他にもあります。東京の根津神社ではかつて須佐之男命を十一面観音菩薩の権現として祭っていました。加えて山王権現と八幡大菩薩を祭り、根津三所権現と呼んでいました。香川県の金刀比羅宮は大物主神を祭りますが、明治までは金毘羅大権現と呼ばれており、松尾寺金光臓という真言宗の寺院でした。このようにそれぞれの権現を祭る寺社があります。寺社は寺院と神社のことで権現を祭るのは寺院と神社の両方です。主な権現とそれを祭る寺社を()に入れました。愛宕権現(愛宕神社)、熊野権現(熊野三山)、金毘羅権現(真言宗松尾寺)、金剛蔵王権現(金峯山寺)、東照大権現(東照宮)、根津三所権現(根津神社)、白山権現(自生山那谷寺)、出羽三所権現(出羽三山神社)、日吉山王権現(日吉大社)、二荒権現(日光二荒山神社)。このように権現は神仏習合がもたらしました。
神仏習合の背景には神道と仏教が合わさることでより信仰を集めたいという思惑があったのかもしれません。神社の境内などに建立された寺院を神宮寺といいます。この神宮寺は奈良時代すでに存在していました。反対に寺院に神が勧請されて守護神(鎮守)として祭られることもありました。平安時代に神仏習合は本格化していき、有力寺院と結んだ神社が大きく発展するケースがみられます。滋賀県にある日吉大社は比叡山の東にあります。かの最澄が比叡山に延暦寺を開くと、もともと比叡山の神だった日吉神は延暦寺の鎮守神となります。延暦寺とつながると「日吉山王」や「山王権現」と呼ばれるようになります。山王とは最澄が天台教を学んだ唐の天台山国清寺に山王が祀られていたことに由来しています。比叡山が絶大な力を持つと神仏習合の山王権現は各地に広がります。その後、天台宗の天海により体系化していきます。徳川家康の側近だった天海は家康の死後、彼を東照大権現として祭るようになります。徳川家康を神として祭るのが全国の東照宮ですが、家康は死後東照大権現という神になり、権現は仏が神の姿を借りたものですから複雑です。
世界遺産である熊野古道で有名な熊野三社。熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の三社からなります。もちろんこれらは神社であり、ご祭神は熊野本宮大社が家都美御子大神、熊野速玉大社が熊野速玉大神、熊野那智大社が熊野夫須美大神です。熊野も神仏習合が進むことで神は「熊野権現」と呼ばれるようになります。権現は上で説明したように、仏が神の姿を借りて現れることです。神仏習合により、熊野本宮大社御祭神の家都美御子大神は阿弥陀如来、熊野速玉大社御祭神の速玉大神は薬師如来、熊野那智大社御祭神の夫須美大神は千手観音が本来の姿とされました。熊野三社は仏教と融合することでより信仰を集めることになります。神道の熊野信仰が仏教の浄土思想と結びつきました。
神仏習合のなかには日本にあった山岳信仰に仏教の密教が融合して成立した山岳仏教である修験道が生まれます。修験道は険しい山に籠もり、厳しい修行に明け暮れます。修行する場を霊場といいます。山岳信仰の一つに北陸と中部にまたがる白山を崇拝する白山信仰があります。その白山を奈良時代に僧侶泰澄が初登頂に成功すると修験道の霊場として発展します。白山権現として信仰を集めてきました。他にも山形県の出羽三山(月山、羽黒山、湯殿山)が修験道で有名です。修験道の祖である役行者もこの地で修行したといいます。羽黒山にある出羽神社では三山の神を合祀し、三所大権現として信仰を集めます。一方、羽黒山には仏教建造物の五重塔や黄金堂があり神仏習合が体現されています。
仏と神様が一緒になった典型例は七福神でしょう。当院のある新宿区にも新宿山手七福神めぐりがあります。七福神が祭られているのは神社・寺院にまたがります。恵地寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、福禄寿、寿老人、布袋。福神といいますが大黒天、毘沙門天は仏像にあります。弁財天も宇賀神と同一視されていますが仏像。最古の七福神めぐりは京都の都七福神まいりとされます。民衆に定着したのは江戸時代。江戸幕府初代将軍徳川家康が、ブレーンにあたる天海僧正の進言により七つの寺社を建立し、これらに祭られた七福神を順に参拝すればご利益がいただけるとしました。スタンプラリーのような要素があり江戸で大流行します。なお東京での七福神めぐりで最古のものは谷中七福神めぐり。神仏習合が庶民に定着している証拠です。
このように明治維新後の神仏分離令が出されるまで神仏が共存していたのです。神仏習合の時代が非常に長いため今でも同一視する習慣が残っています。都内最古の寺院とされる浅草寺。広い境内と立派な本堂がありますが、その横に浅草神社があることを知る人がどれくらいいるでしょうか。有名な三社祭りは浅草寺ではなく浅草神社が取り仕切ります。お祭りは神道。そのことを認識している人は割と少ないと思われます。神仏習合の実例を知ることで神社と寺院の関係がより深くなります。
甲野 功

 大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
コメントをお書きください