開院時間
平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)
土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)
休み:日曜、祝日
電話:070-6529-3668
mail:kouno.teate@gmail.com
住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202
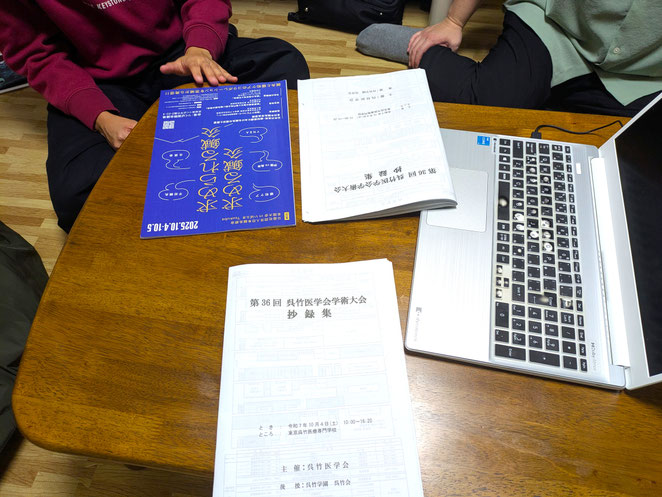
当院で鍼灸マッサージ専門学校に通う学生さんを招いて学会やイベント等の報告会を開催しました。以前からよく勉強に来ている学生さん達。各種学会や業界イベントに参加しています。私が参加しなかったそれらのことを聞き、私が参加したものについても話すという内容です。普段は私がずっと話しているパターンが多いので、各自話す場にしたいと思い、いつも作成するプレゼンテーション資料は用意しませんでした。学生さん達は各自抄録やメモ書きなどを持参。スマートフォン、タブレット端末も。座談会形式で机を囲んで行いました。
今回情報共有したものは日程順に以下の通り。
・東洋療法学校協会第46回学術大会
・第36回呉竹医学会学術大会
・第20回日本鍼灸師会全国大会inいばらき
・AMASHI fes 2025
・第35回日本伝統鍼灸学会学術大会東京大会
まず東洋療法学校協会学術大会。これは東洋療法学校協会に加盟している学校の教員・学生でないと会場に入れませんので(特別に入場することはできるのでしょうが)、私はどんなことをしているのか興味がありました。現在、母校の東京呉竹医療専門学校では学生の出席が推奨されているようですが私が学生の頃はその存在自体知りませんでした。東洋療法学校協会は業界内の組織で教育分野の団体。公益社団法人です。在校生の研究発表があり、かつ賞が与えらます。研究発表のコンペティションでもあります。一度も会場に入ったことがないので興味がありました。周囲の専門学校専任教員をしている者は引率で会場にいくと聞いていましたし。
ここで参加した学生さんに気になる発表を尋ねました。内容をどれくらい理解して説明できるか試した部分があります。というのも学会に行きました、発表を聴きました、凄かったです・勉強になりました、では勿体ないわけです。1年生のうちはそれでいいかもしれませんが何を得て、次にどう活かすかまで考えてもらいたいですし、そうした方が成長します。特に今年から正式派出されたあはき・柔整広告ガイドラインという広告に関するルールでは学会発表、論文の内容は広告にあたらないとしています。つまり学会発表を上手に利用できれば貴重な広告手段になるのです。そのためには一般の人に分かりやすく説明できることが大事。東洋療法学校協会のことと共に聴いた発表を理解して人に伝えることの大切さを話しました。
次に呉竹医学会。こちらは私も参加しました。学生さんには参加した人とそうでない人がいました。参加した学生さんが気になった発表。私が注目した発表。参加しなかった学生さんからの質問。そのような議論になりました。呉竹医学会は学校法人呉竹学園の学術大会で、東京校、横浜校、大宮校の3校合同で行われます。鍼灸、あん摩マッサージ指圧、柔道整復の分野で研究発表や症例報告会があります。また外部講師を招いての教育講演や実技セッションがあるのが特徴です。東洋療法学校協会学会と呉竹医学会両方に参加した学生さんの意見として、発表スライドが見やすいという声がありました。どちらも学生発表をみてスライドのレイアウトや内容が呉竹医学会の方が見やすかったという。卒業生として嬉しいです。キーワードとしてアナトミートレインや抗重力筋に対する刺激が出ました。同じ学生の研究発表で自分だったらどうするかを思案していたようです。
私は統計処理や実験プロトコルの解説を加えました。統計処理をした結果のp値がやけに良い数字なっているもの、実験方法がもっと工夫できたら良かったのではないかなど。いざ実験をしてみないと思っていたようにはいかないことが当たり前。そのために先行研究の調査、予備実験、思考実験(想定)などをしてスケジュール調整を踏まえて実験に臨まないといけません。また抄録から何を読み取るのかも話しました。事前に読める抄録から研究の概要を理解し、実際の発表からその想定通りなのか違うのかを知り、必要があったら質問する。そのような経験を積んでいきましょうという。
そして質問があった黒澤一弘先生の指圧実技セッション。これはかなり細かいというかマニアックで私も理解できている範囲で解説しました。太極拳の動作、関節を弛緩させる、作用・反作用の法則を用いる、引きの指圧。私のやり方と比較しながら説明。本当に合っているのか判断できないところもありますが、会場で聞いた学生さんにもいなかった学生さんにもなるべく分かるように話しました。
呉竹医学会と同日開催の日本鍼灸師会全国大会。2日間行われて呉竹医学会から日本鍼灸師会の会場に向かった学生さんにその様子を聞きました。まず日本鍼灸師会は業団と言われる主に開業鍼灸師のための業界団体です。公益社団法人です。この少し前に同じく業団である公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会の「第24回東洋療法推進大会in石川」が1週間前に開催されています。こちらはあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師の団体。鍼灸に関して公益社団法人が2つあることが長らく問題になっています。厚生労働省(国)も医師会もどちらが鍼灸業界の代表団体になるのか?ということです。別々に活動することでまとまらない。更に日本鍼灸師会全国大会には公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会も参加していました。日本あん摩マッサージ指圧師会はあん摩マッサージ指圧師のための業団です。公益社団法人が3つあることが状況を複雑にしていることは間違いないわけです。そして日本鍼灸師会と日本あん摩マッサージ指圧師会が一緒にイベントができるのならば、全日本鍼灸マッサージ師会も参加できないのかという素朴な疑問が生まれるでしょう。聞いた話によると全日本鍼灸マッサージ師会東洋療法推進大会(石川県で開催)にも日本鍼灸師会全国大会(茨城県で開催)にも厚生労働省関係者が参加したとのこと。統一したらいいのにと思うのですが実現しない状況がずっと続いています。
このように学術大会ではなく業団の全国大会である日本鍼灸師会全国大会。その特色が発表に出ていると私は資料をみて感じました。特に鍼灸をより医療として打ち出し医師と連携していこうとする先生と文化として世間に根付かせたいというスタンスの先生の座談会について参加した学生さんが説明していました。会場にいませんが説明を聞くだけ想像できました。そこから鍼灸の立ち位置について学生さん達と議論しました。
続いてAMASHI fes 2025(あましフェス)。あん摩マッサージ指圧師、あん摩マッサージ指圧学生が東京都あきる野市の里山に集まって交流するイベントです。今年初開催で私はコアメンバーのサポートをするメンバーでした。2日間に渡って泊まり込みで行われたあましフェス。写真と共に内容を説明。どのようなことがあったのか、どんなメンバーが来たのか。対面なのでかなり細かいところまで話をしました。そしてこのイベントが業界内で大きなインパクトであり、画期的なものかを説明。時代の転換点になるのではないか、とまで語りました。鍼灸に比べてあん摩マッサージ指圧師は活動が活発ではないし、他校との交流もない。しかしここ数年であん摩マッサージ指圧師達の交流イベントが増えて動きが出てきています。個人の開業あん摩マッサージ指圧師が流派(出身専門学校)の垣根を超えて集まったことは本当に意義があることだと私は信じています。あましフェスから個々の交流ができ、関西でも行おうという動きが始まったことを伝えました。数年後資格を取る学生さんに流れができてきたということを力説しました。
最後は日本伝統鍼灸学会。例年、船堀で開催されます。私は一度だけバイトでスタッフとして参加したことがあります。ここはかなり深いというかマニアックというか、鍼灸の中でも伝統と言われるカテゴリーの学会です。何が伝統鍼灸なのか、という問いにその答えは曖昧だと思われます。日本ですら1000年前からある鍼灸でどこから伝統と呼べるのか。数十年くらいの歴史でも伝統だという流派は。明確な定義はおそらくないでしょう。現代的な解剖学・生理学を基盤として現代医学に即した鍼灸ではない考えや概念で行っている鍼灸全般が伝統鍼灸学会に多いのかと私は考えています。
参加した学生さんの感想として発表会の雰囲気があると。学術的な研究よりもうちはこのようなやり方をしていますよという報告。そして教科書で習う内容と異なったものがあり混乱する発表もあったそう。一方で名人や達人と言われる先生が多数登壇し、噂でしか聞いたことのない流派を目の当たりにできたという声も。私も伝統鍼灸は得意ではない分野なので説明を聞き、資料を読み、そうなのかという反応ばかりでした。
直接伝統鍼灸ではありませんが盛り上がったテーマが被災地支援の鍼灸です。そのようなテーマでの講演が日本伝統鍼灸学会であったとの報告を受けて。母校の東京呉竹医療専門学校鍼灸マッサージ科・鍼灸科では「災害と鍼灸」というテーマの授業があります。災害時にこの職業がどのようなことができるのかを深く考えます。私は柔道整復師でもありますので阪神淡路大震災のときに柔道整復師が活躍したという話を知っていて、緊急事態における柔道整復師の力を期待しています。一方でどちらかと言うと慢性疾患の対応が強く、鍼やお灸(艾)が消耗品である鍼灸が被災地で貢献できる時期は被災直後ではないと考えます。更に被災地へ支援しに行くだけでなく自分自身が被災者になったら、生活圏が被災されたら、という想定も必要ではないか。そのような議論を参加した学生さんとしました。
結局5時間に渡り報告と話し合いが続きました。今まではこちらが話す一方だったものから、学生さんが情報を提供し意見をいうというスタイルになった集まり。成長を感じ、私にとっても有意義な時間でした。
甲野 功

 大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、
東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分
◆小さなお子さん連れでも入れる
◆社交ダンサーに特化
◆地域密着総合治療院
コメントをお書きください